第2章 荒船風穴と西条州の養蚕――かぶらの里は近代産業発祥の宝庫
(3)南牧村:武士のいのちを研ぐ砥石-―天領南牧の砥石
製糸場のある地は、もともと幕府直轄の南牧村砥沢で産出する砥石のデポとして整地された土地であったことはご紹介した。
富岡から信州姫街道(下仁田道)と呼ばれた国道254号、西上州やまびこ街道を西に進むと、ネギとこんにゃくで知られる下仁田町にでる。上州電鉄の下仁田駅付近を左に折れて県道45号線を進むと南牧村に至る。南牧村は養蚕も盛んだったが、同時に良質の砥石が採掘されることでも知られていた。
質としては、荒砥ぎの後、最終仕上げの前に使われる中砥に分類される。砥石としては最も多く使われるものだ。
そのため、徳川の時代になると幕府直轄の天領とされ、南牧で採掘される砥石が幕府の御用砥とされた。逆に言えば、その占有権を持ちたいがために幕府が直轄地としたという土地なのである。
刀剣が、武器としてだけでなく工芸としても高度に洗練されていく中で、武士の魂を磨く道具として砥石がいかになくてはならないものであったかを物語るものである。
採掘された砥石の一部は、旧尾沢小学校の校舎を利用した南牧村の民俗資料館に展示されている。農具や養蚕器具などの資料も展示されており、ぜひ見ておきたい。
また、同館に至る南牧川沿いの県道45号線は、両側に木造2階建て家屋が連なるかつての面影を残す数少ない街道だ。このたたずまいもぜひ保存しておきたいものだ。



星尾風穴
南牧村民俗資料館前を右折し、南牧川から分かれて星尾川を約15分ほどさかのぼると、星尾大橋の手前・左手の畑の上に星尾風穴がある。規模的には小さいが、1905年(明治38)1月の創業で、産業遺産として登録された荒船風穴、東谷風穴よりも早くから利用されていた貴重な施設である。
掘って石で囲った風穴(間口2間(約3.6m)、奥行3間(約5.5m)、高さ10尺(約3m))に貯蔵庫を造り、蚕種約2万枚を貯蔵した。貯蔵温度は、4.4℃~7.8℃で、貯蔵小屋がなくなって風穴がむき出しになったいま、流れ出てくる冷気が真夏でもひやっと涼しい。まさに天然の冷蔵庫である。風穴の右並びに管理事務所があったがそれもいまはない。文化財の指定はないようで、できればしっかりと保存したいところだ。






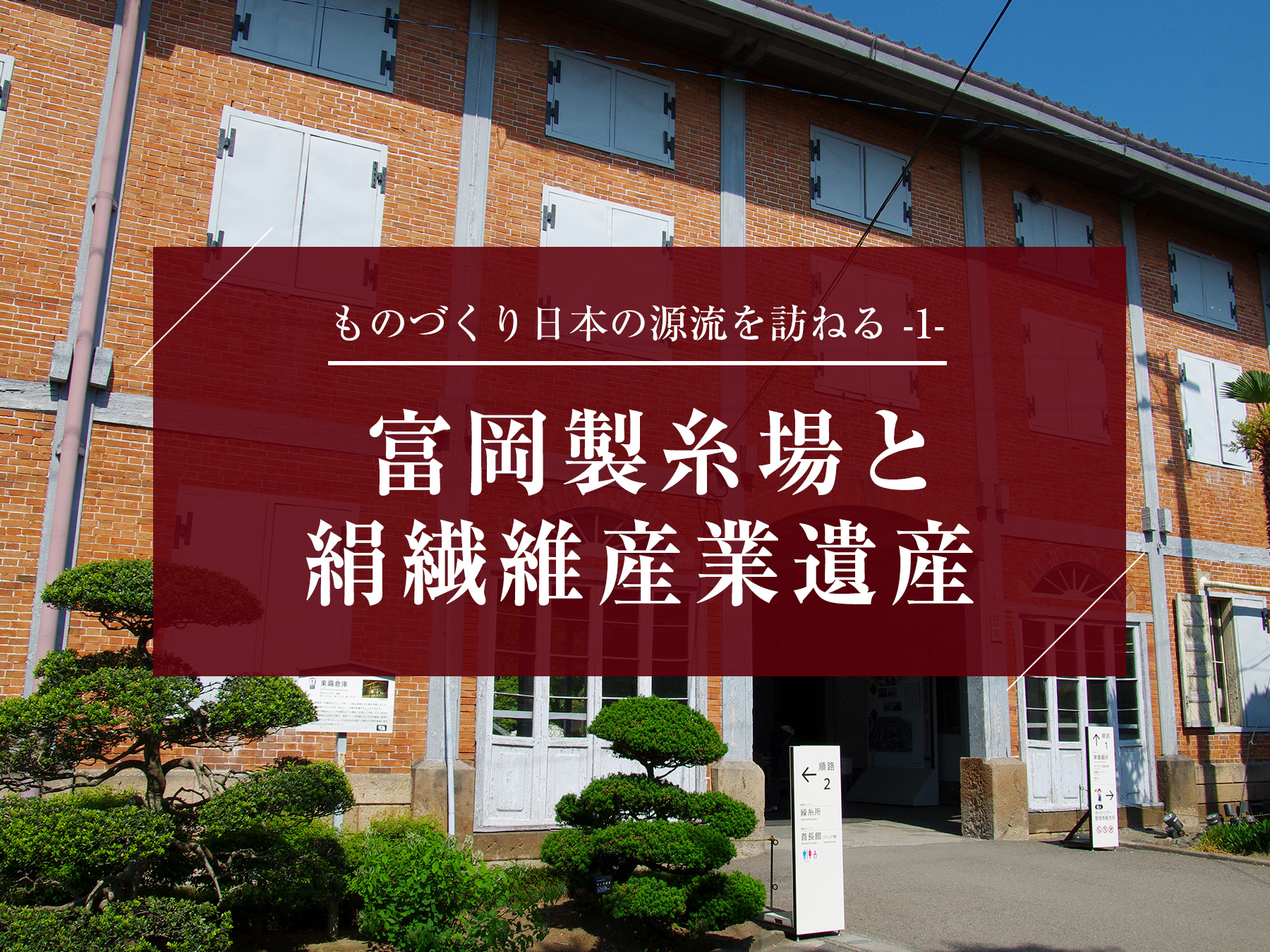
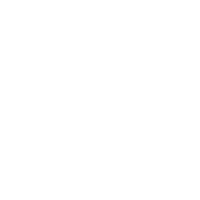 最新情報
最新情報