ものづくり日本の心
第2章:日の丸演説
文:梶 文彦写真:谷口 弘幸(Penthouse STUDIO)
■目次
発端は四ハイのジョーキセン
日本の産業の近代化は、黒船の来航がきっかけで始まりました。
後に鎖国と呼ばれることになる、江戸時代の二百数十年間、私たちは長崎・出島を通じてオランダと、さらに対馬や琉球を経由して支那や朝鮮とわずかに交易を行うだけで、実態は、ほぼ、世界史の舞台から隠れて、ひっそりと泰平の眠りを味わっていました。。
その間、西欧では自然科学が学術的にも実践面でも大きく進歩をとげていましたが、日本国内では相変わらず豊かな自然の恵みをうけて、四書五経を素読みで学ぶ世界にありました。。
そんな状況のなか、黒船がやってきて、門をたたきます。。
ペリー率いる、4ハイの蒸気船が浦賀に姿を見せたのは、1853(嘉永6)年7月です。ペリーは和親条約の締結と開港を幕府に迫り、1年後に回答するとの約束をひきだしていったん日本を離れます。その対応は、やさしく「コン、コン」とノックしたなどというやわなものではなく、英語で何というかわかりませんが、訳せば「いつまで寝とるんじゃ。早よ、門を開けんかい!」という脅しまがいの催促です。。
当時の日本は、寛永12(1635)年に武家諸法度で定めた「五百石積以上の軍船は建造してはならない」という「大型船建造禁止令」のもとにありました。大型の船を持つことは、兵站に大きな機動力を持つことになるとして、諸大名の反乱を恐れた幕府が大型帆船や軍船の建造を禁止していたのです。。
そのため、せいぜい五~七百石から千石(積載荷重150トン、排水量200~300トン)ほどの大きさの、「朱印船」と呼ばれるジャンク型1本マストの「弁才船」が建造され、北前船などの内運に使われているにすぎませんでした。外国貿易が制限されていた状況では、大型の外航船の必要がなかったのです。。
そんなところへ、突然、東京湾の入り口に、千石船の十数倍の大きさの積載量2,450トン、乗組員300名の巨大な蒸気船の軍艦サスケハナと、1,693トン、乗組員260名のミシシッピが、大きな帆船プリマス(989トン、260名)、サラトガ(882トン、260名)を従えて現れたのです。。
「泰平の眠りを覚ますジョーキセン、たった四杯で夜も眠れず」と狂歌にも歌われた事件です。もちろん夜も眠れなかったのは幕府の首脳。庶民はその幕府のあわてぶりを、当時人気のあった銘茶「上喜撰」にひっかけて、四杯も飲んでは興奮して眠れないはずだ、と揶揄しています。。
見るからに巨大な外国軍艦の来襲に、国じゅうが危機感をもって騒ぎ出すかと思いきや、庶民はあたふたとあわてふためく幕府を茶化して笑いとばす余裕があります。何ともじつに頼もしい限りではありませんか。
開国――脅しに屈して不利な条約を締結
狂歌では四杯のジョーキセンとうたわれていますが、正式には、蒸気船は2ハイで、残りの2ハイは帆船でした。それにしても秀逸な狂歌ですね。現代なら、たちまちマスコミが騒いでコピーライターとして時代の寵児になっているでしょう。これだけの歌が読み人知らずとは、評価が低い。日本人がいかに、サブカルチャーをないがしろにしてきたかを物語っています。
江戸幕府は長い間、海外との交易を厳しく制限していました。その間も長崎・出島にはオランダ船が来航していましたし、唐船も来ていました。しかし、いずれも帆船です。
蒸気船が日本にやってくるのは初めてでした。スクリューが導入される前の外輪型です。黒塗りの船体から巨大な煙突がそびえ立ち、石炭のボイラーから煙をもうもうと吐きだす蒸気船の異様な姿に、なにごとかと物見高い野次馬が集まり、幕府はとうとうアメリカ軍艦の見物禁止の触れを出さざるをえなくなりました。
そして半年後の翌1854(嘉永7)年1月、今度は計九隻で神奈川沖にやってきて、江戸湾深くにまで侵入してきます。前回、幕府に一年後の回答を約束させながら、半年後に、しかも九隻もの艦隊でやってきたのは、早く回答せよとの圧力をかけるのが狙いでした。
当時、日本をめぐる情勢は決して安穏としたものではありませんでした。
1840年ころから盛んに欧米の船が日本の周辺を行き来し、国内ではこの対策が求められていました。オランダから入ってくる情報から、日本が技術的にも遅れていることに多くの藩も気づき始めます。開けた先進的な藩の首脳たちは、こうしたことに危機感を持ち、長崎に人を派遣して情報を収集させます。海外の情報を集めれば集めるほど、進んだ技術や文化を学ぶ必要性を痛感します。
江戸湾深くに侵入して脅しをかけられた幕府は、3月に日米和親条約を締結し、下田・函館港を開港してこれに対応しました。そして、そのあと、1858(安政5)年日米修好通商条約に続いて、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも和親条約・修好通商条約を結び、翌59年に、通商のために函館・横浜・新潟・神戸・長崎の5港を開港する約束をします。
脅され、せかされた末の日米修好通商条約の締結で、したたかな相手の戦略に翻弄されて、条約の内容も、アメリカ側に領事裁判権(日本国内で、アメリカ人が起こした事件はアメリカ領事が裁判を行う権利を有する)を認め、日本に関税自主権がなかったなど、決して対等な条約ではありませんでした。
通貨(円―ドル)の交換レートにしても不利な条件で妥結してしまい、明治政府はその後、1860(万延元)年の遣米使節団などでもこの条約の改正交渉に苦労することになります。
幕府は、いくつかの国と修好通商条約を締結し、五港を整備して開港しましたが、それで日本人の海外渡航が自由になったわけではありません。貿易、輸出入が行われるようになったといっても、取引はもっぱら外国商人が日本の港にやってきて、5港で取引をするだけ。日本人の海外渡航禁止令は、解かれていないのです。
サムライたちの海外留学
海外の事情を学ぶ必要を痛感したいくつかの藩は、留学のための渡航申請を幕府に出すのですが、はねつけられます。1854年、吉田松陰が海外への渡航を志願して黒船に潜り込もうとしますが、幕府から渡航禁止を伝えられていた黒船側が乗船を拒否し、松陰が捕縛されるという事件が起こります。
国内は相変わらずそんな状態でしたが、幕府は、通商条約の批准書の交換や海外視察の機会を利用して各国に使節団を派遣し、その際に、留学生も送り出します。その最初が万延元年(1860年)の遣米使節団です。
咸臨丸での太平洋横断が快挙のように伝えられていますが、使節団の中心メンバーは全長77メートル、船幅14メートル、排水量3,765トン、蒸気外輪の米軍艦ポータハンで渡航し、帆船・咸臨丸(排水量620トン)は、米軍航海士たちの支援を受けた日本人訓練生による練習航海といったところでした。
こんな状態でも、一般の海外渡航は禁止されたままです。海外渡航を独占・先行する幕府の姿勢にいら立って、いくつかの藩は、勝手に留学生を送り出すようになります。
1863(文久3)年に長州藩は井上馨、伊藤博文ら5名をイギリスに留学させます。1864年には安中藩の江戸詰め下級武士だった新島襄が函館からひそかにアメリカに脱国。1865(慶応元)年には薩摩藩が森有礼、五代友厚ら19名をイギリスに留学させ、他に佐賀藩、土佐藩なども留学生を派遣します。
伊藤博文たちの渡航は、のちに長州ファイブと呼ばれるようになりますが、これらはいずれも長州藩や薩摩藩が派遣したもので幕府が認めたわけではありません。
日本人の渡航は解禁になっていませんから、旅券の制度もありません。上記の全員は厳密に言えば国禁を犯しての密航です。長州藩や薩摩藩の旅券なしでの留学を助けたのが、長崎に滞在していたジャーデン・マセソン商会のグラバーだったと言われています。
それにしても、1858年に日米修好通商条約が結ばれ、翌59年に5港が開港してすでに数年が経過しています。通商を可能にしておきながら、もっぱら外国商人が買いに来て、港で取引をさせるだけで、日本人が外国に売り/買いに行くのはご法度です。この一方的な交易の体制は、いかに幕府の意識が遅れていたかを示すものと言えるでしょう。
そんな環境の中で、庶民の意識はどうだったかといえば、例えば、こんな状態だったのです。
「中津川の商人、萬屋安兵衛、手代嘉吉、同じ町の大和屋李助、これらの人たちが生糸売込みに眼をつけ、開港後まだ間もない横浜へとこころざして、美濃を出発してきたのはやがて安政六年の十月を迎えた頃である。・・・」。
これは、木曽路はすべて山の中である・・・で始まる島崎藤村「夜明け前」の第四章の書き出しです。
安政6年10月といえば、西暦に直すと1859年11月。幕府が通商条約で約束して5港を開港したのが同年6月1日のことです。木曽の山の中の商人でさえ、開港した4か月後には、生糸を売りに横浜に出ようかという状況だったのです。
この好奇心旺盛にして、時代の流れに遅れてはならじ・・・と迅速に行動する庶民の機動力と比べて幕府の対応のいかに遅いことか。
多くの藩からの要望もあり、幕府が、学術・商業のために「海外行き許可の認証に関する布告」を発布するのは、1866(慶応2)年4月7日(新暦:5月21日)のことでした。
ここではじめて民間人の海外渡航が可能になるのですが、この時、日本国政府発行の第1号旅券を取得して海外に出たのは、幕府や雄藩の侍たちではなく、なんと手品師・曲芸団で、国内に来ていた興行師に誘われてアメリカ公演に出た一行だったそうです。
海外が宇宙と同じように謎の多い国で、出かけていくには決死の覚悟が必要だった時代のことです。私たちの先輩は、いまの私たちが考えるよりも、ずっと好奇心旺盛で前向きな人たちだったのかもしれません。
この間に、薩長などが英・米・仏・蘭などの国と薩英戦争、下関戦争・馬関戦争などを経験。彼我の軍事力の格差の大きさを目の当たりにした幕府は、攘夷は不可能であることを知り、欧米から技術を学んで軍事力を強化するという方向に政策を転換します。
攘夷から開国へ180度の転換
この後日本は、1867(慶応3)12月9日(新暦1868年1月3日)の王政復古の大号令を受けて、翌年1868年9月8日(新暦10月23日)を明治元年として薩長土肥を中心とした新政権が誕生しますが、「攘夷」を掲げて奪取した新政権は、政権を取ると幕府の政策を踏襲し、富国強兵策を柱にした「開国」へと180度の政策転換をします。
旧暦/新暦の記述が紛らわしいのですが、それまで採用されていた太陰暦(天保暦)が、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に変わったのは明治5年12月3日からで、この日を 明治6年1月1日として新暦に移行しました。その結果、明治5年は12月が2日しかありません(これ以前は旧暦、以降は新暦で記述します)。
国をリードする根本政策が、政権奪取後に「攘夷」から「開国」へと大きく変わるのですが、このあたり、与党(野党)の政策に反対をマニュフェストに掲げて選挙戦に挑みながら、政権を取った後は、すっぱり主張を忘れて真逆の政策を推進する、と現代風に翻訳してみると、なにやらどこかで聞いたことがあるようなお話になります。それがあまり大きな問題にもならずに通ってしまうところは、日本人の国民性なのかもしれません。
とはいえ、ヘアピンカーブさながらの急転換を行ったことで、明治維新政府はその後の政策運営に苦慮することになります。
しかし、開国・富国強兵と決めてからの思い切った対応で、こうした苦境を見事に乗り切ります。一つは、国のかじ取りを担当したのが、怖いもの知らずの30代の若い世代だったということ、さらに、江戸時代に培われた日本人の基本的な素養・能力が、大きな転換にあたっても十分に対応できる高いレベルで確立されていたこと、なによりも政府首脳に外国の侵略から国を守り自立させたいとの強い思い・・・が大きな力になった気がします。
そして、維新直後の1871(明治4)年11月12日、国のゆくべき方向を見極めるため、岩倉具視を大使として欧米に使節団がでかけます。
新しい政府が組織されて、やっと廃藩置県が行われたばかりのころです。
藩が廃止され、藩から禄をはんでいた武士たちは職を失いました。幕府の家来、旗本などの幕臣も同様です。全国の侍たちが一挙に職を失うことになるわけですから、何とか生きる道を考えてあげないといけません。
新しい国のスタートにあたって、やることは山積している状態で、伊藤博文、大久保利通、木戸孝允、山口尚房という最高首脳がそろって国を留守にして、海外の視察に出かけました。
使節団総勢46名、これに随従が15名、官費・私費の留学生42名を加えて総勢103人の一大デレゲーションです。しかも期間は1年9か月。欧米事情を知りたいという気持ちは分かりますが、これを意思決定し、実行した当時の首脳たちのとてつもない好奇心、向学心、そしてなによりも胆力に驚きます。この視察の成果は「特命全権大使米欧回覧実記」(*①久米邦武著)として報告されます。
名前は「特命全権大使」となっていますが、実は、天皇陛下からの信任状を持参していないことをアメリカから指摘されて、あわてて取りに帰国するなどの失態もあり、その後は、全権大使の公式名を外し、「使節団」と称しています。
31歳伊藤博文の英語スピーチ
明治4(1871)年、岩倉使節団は最初の訪問国アメリカで大歓迎を受けます。サンフランシスコに到着した翌日の12月14日にグランドホテルで歓迎の晩さん会が開催されるのですが、その席で伊藤博文は通訳なしの英語でスピーチを行います。
1841年に長州で足軽の子として生まれた伊藤博文は秀才として名高く、青年となって吉田松陰の松下村塾で学びます。1863年に長州藩から派遣されてイギリスに留学しましたが、翌年、長州藩がイギリス・フランス・オランダ・アメリカの四国を相手に下関戦争を仕掛けたことを聞いて、それを止めるために留学を一年で切り上げて帰国。また、71年には半年ほどアメリカ・ワシントンに法律を学ぶために滞在しています。
当時のアメリカは、1776年の独立から100年、進取の気象に燃えた若い国でした。広い国土の割に人口が少なく、ヨーロッパから多くの移民を受け入れていました。移民とともにヨーロッパの産業技術や知識を輸入することもねらいでした。
こうしてイギリス、フランスなどから移り住んだ若い技術者たちは、自由の地で本家をしのぐ発明・改良を進めて産業を急成長させます。ヨーロッパの諸国から見れば、アメリカは開発途上国。技術も作られる商品も、粗削りで、品質的にはいまひとつの感はあったようですが、それでも、それまで見られなかった新しい工夫がそこここに加えられていて、価格もリーズナブル、ヨーロッパ諸国でそれなりの市場を獲得し始めていたところでした。
アメリカとしては、ヨーロッパに次ぐ新しい販売先としてアジアの開拓を目指している時期で、当時盛んだった捕鯨船団への補給基地として、また中国などアジア諸国への燃料や食料、水を補給するための中継基地として、日本は重要な位置にあると考えていたところでした。
アメリカの市民から見れば、日本は、ペリー艦隊を派遣して開国させ、世界で初めて和親条約を結んだベールに包まれた国として、世情的にも多くの国民が関心を持っていました。町中がウェルカムという雰囲気の中での視察団の訪米であり、伊藤博文のスピーチだったわけです。
その頃のアメリカは、スピーチが大流行していたそうです。人々はスピーチを楽しむためにパーティや晩さん会、演説会を開き、そこでお互いの弁舌を競ったそうです。そのため、スピーチを収録した講演録集なども販売されていました。
そんな背景の中で行われた伊藤博文のスピーチは、流れるような英語というわけにはいかなかったようですが、それでも終わった後、しばらく拍手が鳴りやまなかったといいます。
外国人を前に、国の将来を思う気持ちと、若さからくる気負いに溢れた、非常に気高いスピーチで、いま私たちが読んでも、強く訴えてくるものがあります。
おどろくことに、伊藤博文は当時31歳。わたしたちの31歳はどうだったかと思えば、内心忸怩たるものを禁じえません。
スピーチはちょっと長いのですが、非常に興味深い内容ですので、全文をご紹介しましょう(主として*②「伊藤博文伝(上)」春畝公追頌会、統正社によります)。以下文中( )内は、筆者付記です。
日本に実施せられたる幾多の改良
吾等使節として当国に到着いらい、到る処にて受けし慇懃なる接待、殊に今夕の特別なる饗応に対し、深厚なる感銘の意を諸君並に諸君を通じて桑港(サンフランシスコ)市民に表す。
惟(おも)ふに今夕は、日本に実施せられたる幾多の改良に就き、精確なる概要を述ぶべき好機会なるべし。蓋(けだ)し我日本人以外には、我国内の状況に就き正確なる知識を有する者稀れなればなり。
条約国――合衆国を以てその最初とす――との親交は維持せられ、我国民の理解に依り通商関係は増進せり。
本使節は、天皇陛下の特命に依り、彼我両国民の権利及び利益を保護するに努むると同時に、将来に於て内外国民の結合を一層親密ならしめんことを期するものなり。我等は互に益々相知るに従ひ、双方の意思は愈々(いよいよ)疎通するに至るべしと確信す。
ここまではイントロ、相手国に対する儀礼とあいさつですね。
当時のアメリカは前述したように、独立を果たして100年、南北戦争も北軍の勝利で奴隷解放が進み、また、大陸横断鉄道も完成したばかり。蒸気機関や産業革命の成果を積極的に導入し、自らも工夫改善を進めて経済発展に自負を持っている時期です。
アメリカ人の日本への知識については、前年、伊藤博文がニューヨークに滞在していたときに、ペリーが帰国後に表した「日本遠征記」が公開されていることを確認し、米国内に「後進国=日本」のイメージが定着しているのを知っています。
そんな空気も感じたのでしょう、伊藤は、「今夕は、日本に実施せられたる幾多の改良に就き、精確なる概要を述ぶべき好機会なるべし。」と述べています。
日本国内では、1865年には横須賀に製鉄所が建設されて戦艦づくりが始められ、使節団が出発する時には、すでに新橋―横浜間の鉄道の工事も始められていて、半年後には品川―横浜間が仮営業します。「日本遠征記」の時代から、十数年が経過した現在、日本は急速に改良を遂げ、いまや昔の日本ではないぞ、ということを伝えておきたい。今日こそ、待ちに待ったその絶好の機会!という気負いがスピーチに溢れています。
文明の最高点に到達せんとする
伊藤は次のように続けます。
我国民は、読むこと、聞くこと並に外国に於て視察することに依り、大抵の諸外国に現存する政体、風俗、習慣に就き一般的知識を獲得したり。今や外国の風習は日本全国を通じて諒解せらる。今日我国の政府及び人民の最も熱烈なる希望は、先進諸国の享有する文明の最高点に到達せんとするに在り。この目的に鑑み、我等は陸海軍、学術教育の諸制度を採用したるが、外国貿易の発展に伴うて知識は自由に流入せり。
日本は、アメリカとの修好通商条約を結んだあと、イギリスやロシア、オランダ、フランス、など5か国と修好通商条約を結んだことで、外国との貿易が開始され、諸外国の政治・風俗・習慣についての情報が入って来るようになりました。
そうしたことから、諸外国の事情はよく理解している。そして、各国の風習なども日本全国に知らされていると述べた後、伊藤はこの視察を通して、日本は何をしようとしているのかを、「今日我国の政府及び人民の最も熱烈なる希望は、先進諸国の享有する文明の最高点に到達せんとするに在り。」と明確に述べています。
つまり、先を進む欧米先進国に追い着き、トップに並びたい、といっているのです。当然、おいつけると思っているのでしょう。圧倒的な差を自覚している中で、この自信はどこからくるのでしょうか。
我国に於ける改良は物質的文明に於て迅速なりと雖(いえど)も、国民の精神的改良は一層遥かに大なるものあり。我国の最も賢明なる人々は、精密なる調査の結果、この見解に於て相一致す。数千年来専制政治の下に絶対服従せし間、我人民は思想の自由を知らざりき。物質的改良に伴ふて、彼等は長歳月の間彼等に許されざりし所の特権あることを諒解するようになれり。尤もこれに伴ふ内変は一時の現象に過ぎざりき。我国の諸侯は自発的にその版籍を奉還し、その任意的行為は新政府の容るる所となり、数百年来鞏固に成立せし封建制度は、一箇の弾丸を放たず、一滴の血を流さずして、一年以内に撤廃せられたり。かくの如き驚くべき成績は政府と人民との合同行為に依り成就せられたるが、今や相一致して進歩の平和的道程を前進しつつあり。中世紀に於ける孰(いず)れの国か戦争なくして封建制度を打破せしぞ。
此等の事実は、日本に於ける精神的進歩が物質的改良を凌駕するものなることを立証す。
我が国にとって、西欧の物質文明の導入は大きな成果を上げているが、我が国の国民にとっては、それよりも、精神的な改良効果の方が、はるかに大きくて重要であり、このことは多くの人間の認める所となっている、と述べ、物質的な改良とともに、長い間許されなかった精神的な自由さも得た。そして、諸大名は、自主的に版籍を奉還し、数百年続いた封建制度は、一箇の弾丸を放たず、一滴の血を流さずに撤廃された、と語ります。
数百年来の鞏固な封建制度が1年もかからずに撤廃され、国民と政府の協力で、平和の裡に国づくりが進んでいる。世界に、戦争無くして封建制度を打破した国は他にあるだろうか。この事実から、日本という国は、物質的な進歩をはるかに凌駕して、精神性という点では進んだ国である……と伊藤博文は誇らしげに訴えているのですね。
政権交代にあたっては、鳥羽伏見の戦い、彰義隊との上野戦争、戊申戦争、函館戦争……などがあり、多くの血が流されました。しかし、肝心の江戸城の開城、大政奉還、版籍奉還までは一滴も血を流さずに話し合いで行われました。伊藤はこのことの意味を訴えたかったのでしょう。
先進国から多くを学び、早く追いつきたいと言いながらも、教えてください……と卑屈になるのではなく、無血革命を実現した精神性の高さはどうだ!と逆にアピールしています。なんとプライドに満ちたことばでしょうか。
このあたりは、2度にわたるイギリス、アメリカへの留学で感じた思いをぶつけたものでしょう。留学で欧米の個人主義や物質的な利益を優先する風潮を知り、その結果、逆に我が国の文化が持つ精神性の高さが世界的にも誇れるものであることを発見した、そんな伊藤博文の経験がここに出ています。
彼我を冷静に比較できるところは、とて31一歳のものとは思えません。
又我が女子を教育することに依り、我等は将来の時代に於て今より一層優秀なる智能の涵養を庶幾(しょき:切望する)するものなり。この目的を以て、我国の少女等は既に勉学の為め貴国に来りつつあり。
この視察団の一つの特徴は、多くの男子に交じって、五人の女子留学生がいたことです。しかも、8歳、9歳、12歳、15歳、16歳と全員が若い。なかでも津田梅子(帰国後に女子英学塾、後の津田塾大学を創設)は数えで8歳、満でいえば6歳という幼さでした。その彼女たちも先進国の英知を学ぶことで、「今より一層優秀なる智能の涵養を庶幾する」と大きな期待を背負っていたのです。
未だ創造的能力を誇る能はず
この後、日本はいまだ創造的な能力に欠けるところはあるが、良い点は積極的に取り入れていくとし、さらに、自らが1年ほど前に滞在したニューヨークでの体験を語り、これまで諸外国から学んだ多くのことは既に実行に移されていると紹介して、今回も学んだことは国に持ち帰って導入したいと述べています。
日本は、猶ほ未だ創造的能力を誇る能はずと雖(いえど)も、経験を師範とせる文明諸国の歴史に鑑み、他の長を採り誤を避け、以て実際的良智を獲得せんと欲す。一年足らず以前に予は合衆国の財政制度を精細に調査したることありしが、その時華盛頓(ワシントン)滞在中貴国大蔵省高官より貴重なる援助を受けたり。而して予の学び得たる各種の事項は、誠実に我政府に報告せしが、その献策は大抵採用せられ、既に実行に移されたるもの少なからず。現に予の管轄下にある工部省に於ても、進歩の大いに見るべきものあり。鉄道は帝国東西両方面に敷設せられ、電線は我領土の数百哩(マイル)に亘(わた)って拡張せられ、数箇月中に殆ど一千哩に及ばんとす。燈台は今や我国の沿岸に設置せられ、我造船所も亦活動しつつあり。此等の施設は総て我文明を助成するものにして、我等は貴国及び他の諸外国に対し深く感銘する次第なり。
日本には、新しいものを生み出す力はないが、文明諸国から良いところを学び、学んだ結果は、即座に反映させていると、鉄道や電線の敷設、灯台の設置、造船所の建設など具体的な例を紹介し、こうしたことへの支援に感謝を述べています。
そしてさらに、今回も多くの情報を持ち帰り、みなさんが発展してきた成果を学び、短時日で通商を増進し、健全なる基礎をつくりたいと述べています。
使節としても個人としても、我等の最大の希望は、我国に有益にして、その物的及び智的状態の、永久的進歩に貢献すべき資料を齎(もた)らして帰国するに在り。我等は固(もと)より我人民の権利及び利益を保護するの義務を負ふと同時に、我通商を増進することを期し、且つこれに伴ふ我生産の増加を図り、その一層大なる活動を助長すべき健全なる基礎を作らんことを望むものなり。
太平洋上に今将に展開せんとする新通商時代に参加し、大いに為す所あらんとする大通商国民として、日本は貴国に対し、熱心なる協力を捧げんとす。貴国の現代的発明及び累積知識の成果に依り、諸君はその祖先が数年を要せし事業を数日にて成就し得るならん。貴重なる機会の集中せる現時に於て、我等は寸陰をも惜まざるべからず。故に日本は急進を望むや切なり。
通商を増進し、生産の増加を図りたいというのではなく、「その一層大なる活動を助長すべき健全なる基礎を作らんことを望む」と言っているのですね。結果を求めるのではなく、結果が生まれる状態をつくりたい、と言う主張です。これは、すごいことですね。
普通であれば、結果を求めるでしょうが、伊藤はそうではありませんでした。言ってみれば、成績の悪い子供が、「成績をよくしたい」というのではなく、「成績をよくできるような習慣を身に着けたい」と言っているようなものです。こんな発想は日本人にもともとあったものでしょうか? 早急に成果を求めるのではなく、体質を変えたいという主張は、聴いていたアメリカ人を驚ろかせたのではないかと思います。
そして最後に、伊藤は以下のように続けます。
日の丸…昇る朝日の尊き徽章
我国旗の中央に点ぜる赤き丸形は、最早帝国を封ぜし封蝋(ふうろう)の如くに見ゆることなく、将来は事実上その本来の意匠たる、昇る朝日の尊き徽章となり、世界に於ける文明諸国の間に伍して前方に且つ上方に動かんとす。
日本の国旗である、白地の中央に描かれた赤い丸は、国を封じる「封蝋」(手紙に封をする蝋のシール)ではなく、「昇る朝日の尊い徽章」であり、「世界における文明諸国の間に伍して、将来に、かつ上方に向かって昇ろうとしているものだ」と締めくくりました。
なぜここで日の丸が唐突に出てくるのか、若干の説明が必要かもしれません。
明治維新で体制が変わった時、まだ日本の国には正式な国旗が制定されていませんでした。つまり、国内はともかく対外国という点で、国家としての体裁が整っていなかったということですね。黒船来航いらい、諸外国と通商条約を締結し、行き来をするようになると、国旗の必要性が生まれてきます。
最初に問題になったのは、船舶です。
公海を渡る船は、その船の船籍を示す国旗を掲示することが義務付けられています。そこで、明治政府は明治3年(1870年)、商船規則の制定に際して、白地に赤丸の日の丸を「御国旗」として規定したのです。
しかし、日本の国そのものが古い封建社会の国とみられていたアメリカでは、この赤い丸は人々を封じ込める赤い封蝋と揶揄されていました。伊藤の演説は、こうした揶揄に対する想いを熱く語ったものでした。
このスピーチは、万雷の拍手でたたえられ、翌日の新聞にはこのスピーチへの賛辞があふれていたそうです。
のちに、「日の丸演説」と呼ばれることになるこのスピーチは、後進国と見下していた東洋の小さな国から来た若者が、英語で演説を行ったというアメリカ人にとっての驚きもあったでしょう。改めて読んでみると、それ以上に、新しい国を作ろうという、伊藤の溢れるほどの熱い思いが伝わった名スピーチといえます。
視察団は、このあと一年半以上にわたって欧米諸国を視察していくのですが、この伊藤博文のスピーチ、国を憂う思い、卑屈にならずに堂々と主張する自負心、そして、先見の明……。後に首相になる人物とはいえ、弱冠31歳でこれだけの演説をやってのけるとは、見事というほかありません。
その後の日本は、このスピーチの通りに歩みました。殖産興業・富国強兵をへて、現在のものづくりの国に通じる出発点を、この伊藤のスピーチにみることができます。
「超ド級」戦艦の完成
さて、維新後に政府は殖産興業・富国強兵をすすめる政策を展開しましたが、最初の課題は製鉄でした。軍事力の増強には、大砲や軍艦が不可欠です。しかし、国内には良質の鉄鋼を量産する技術や、大砲、大型軍艦をつくる技術がありません。
古来、日本の鉄づくりは、砂鉄を採集し、木炭で加熱し、たたらと呼ばれるふいごで風を送って高温にして溶かす、たたら製鉄法が用いられてきました。これで作られる玉鋼は、硬さがあって曲がりにくい特徴があり、刀剣の切れ味を向上させたり、農具、生活用具などを作ったりするには良いのですが、しなりがなく曲げると折れてしまいます。柔軟性が求められる構造物には適しません。
そこで、たわんでも折れにくい均質な構造物用の鉄鋼を生産するために、西洋式の反射炉・高炉などの製鉄技術が導入されました。
同時に、長崎・横須賀に造船所を作って船舶の建造の準備をすすめる一方、イギリスに戦艦を発注し、技官を送って、軍艦づくりのノウハウを学ばせます。そして技術を持ち帰った技官らが中心になって、自力で建造する道を歩みます。このときイギリスに発注されたのが、後に日露戦争(1904-05年、明治37-38年)で旗艦となった「三笠」(1902年完成)などでした。
その後、広島・呉、神戸に造船所をつくり、各地で競うように軍艦が作られていきます。こうして我が国で初めて西洋式の戦艦が作られたのが一九一〇年(明治四三年)、広島・呉の海軍工廠で「薩摩」です。全長137.2メートル、排水量19,372トン、推力は石炭による焼玉エンジンです。
続いて、大正時代になると、巡洋艦「榛名」(26,330トン、1914年神戸・川崎造船所)、「霧島」(27,000トン、1915年長崎・三菱造船所)を建造。
1920年(大正9年)になると、世界最強35,000トン級の戦艦「長門(呉工廠)」、「陸奥(横須賀海軍工廠)」を作りあげるまでになります。
この長門、陸奥は、当時世界最強と言われた英国の戦艦「ドレッドノート」(1906年竣工)を上回る航行速度や大砲などを備えた戦艦として建造され、「ドレッドノート」を超えることから、スーパー・ドレッドノート・クラス=「超ド級」ということばで呼ばれるようになりました。
最近は、甲子園で活躍する選手に「超高校級」「超ド級」などと使われたりしますが、もともと「英国の戦艦ドレッドノート」から生まれた表現でした。
黒船が来航した当時、日本の産業技術力は西洋と比較にならないレベルでした。その日本が、富国強兵をめざして50年後、自力で最初の軍艦を作ってからわずか一〇年後にはイギリスに追いつき、それらに匹敵する世界一のレベルの戦艦を建造する能力を持つまでに至ったのです。ノウハウを学び、応用する能力とキャッチアップの速さ、ものづくりへの適応性は見事というほかはありません。
つい50年ほど前まで、世界史からこぼれ落ちていたような東洋の小さな未開の国が、またたく間に力をつけて、列強をしのぐ軍艦を建造するようになった、その潜在力は、列強の目には、大きな脅威と映ったに違いありません。
世界のパラダイムを変えた日本のものづくり
西欧を目指して追いつけ追い越せで突き進んできた日本は、その猪突猛進の勢いのまま第二次大戦まで突っ走ってしまいました。軍事力で列強に並んでからの迷走ぶりは、いかんともしがたいところがありますが、目標を決めてゴールを目指す時に発揮する集中力とパワーは、列強に対して日本という国の潜在力を強く意識させることになったと思います。
しかし、世界一の軍艦を建造したといっても、実態は付け焼刃で、インフラの整備や社会的な蓄積は金メッキのような薄っぺらなものでしかありませんでした。キリのような鋭角な切っ先に全リソースを投入して一点突破には成功しても、そうした力や資産を社会全体に配分して、国民の豊かさ、底辺の底上げにつなげるという方向には使われませんでした。
国策として力を入れ、獲得してきたその技術力や経済力を、列強に伍して領土拡大に投入するのではなく、国民の福祉と生活の向上に投入していれば、日本はまた別の国になっていたかもしれません。しかしそれはいまだから言えることで、当時はそんな状況ではなかったとおもいます。
大航海時代以後、世界をリードしてきたのは、欧米の国々でした。一九世紀後半に欧米諸国が集まって作った国際法「万国公法」では、欧米の「文明国」は、アフリカなどの「非文明国」や、アジアの「半文明国」に対しては、
- 不平等条約などをもって国交・通商を迫り、
- 万一それを拒む場合には、武力によって受け入れさせることが正当な行為
として認められていました。
そのため、彼らは競ってアジア、アフリカ、南米へと進出し、植民地化を進めました。
ペリーが1853年7月に来航し、1年後の回答を約束させながら半年後の1854年1月に再びやってきて、条約の締結を催促した裏には、こうした文明国の半文明国への恫喝があったわけです。植民地化の危機は、日本にも迫っていたのです。
世界史的に見れば、それまで、欧米以外の国が、列強に伍して政治・経済・技術面で台頭してきたことはありませんでした。そんな時代に、半文明国とみなされていたアジアの一小国である日本が、開国以来、急速な発展を遂げて、世界の舞台に飛び出し、自己主張を始めたのです。
彼らにとってみれば、圧倒的な力の差で面倒を見ていたはずの幼な子が、あれよあれよという間に大きくなり、力をつけてやがて背伸びを始め、気が付けば、おれの方が強いぞと分け前を要求するまでになっていたということでしょう。
力をつけてからの国のあり方に議論はあるとしても、経済力で「半文明国」とさげすまれていたアジアの中から、初めて日本が列強(文明国)の仲間入りをしたという事実は、世界史的にもそれなりの価値と栄誉を持って語られてもいいのではないかと思います。
そのベースとなったのが、私たちの先輩が発揮したものづくりの力でした。
ブータン・ワンチュク国王のメッセージ
2011年11月17日、日本を訪問したブータン王国の若きワンチュク国王は国会で演説を行いました。その中で日本に対する思いを次のように語ってくれました。
「2011年は両国の国交樹立25周年にあたる特別な年であります。しかしブータン国民は常に、公式な関係を超えた特別な愛着を日本に対し抱いてまいりました。私は若き父とその世代の者が何十年も前から、日本がアジアを近代化に導くのを誇らしく見ていたのを知っています。すなわち日本は当時開発途上地域であったアジアに自信と進むべき道の自覚をもたらし、以降日本のあとについて世界経済の最先端に躍り出た数々の国々に希望を与えてきました。日本は過去にも、そして現代もリーダーであり続けます。」
ワンチュク国王は、日本を高く評価していると話してくれたのですが、わたしたち自身がこうしたことをどれくらい認識しているでしょうか。
いま、アジアの時代と言われています。中国を中心としたアジアの国々の経済発展が注目されるようになったのはほんの最近です。百数十年前のアジアは、多くの国が欧米諸国によって侵略され、植民地として蹂躙され、資源の収奪が行われていました。
そんな中で、日本は西洋文明に出会っても屈服せずに、その知識や技術を取り込んで自分のものとし、産業を興してやがて列強に並ぶほどの力をつけました。
その意味で開国は、日本にとっては国内改革の大きな契機でしたが、同時に、欧米列強の覇権主義に対して、遅れた「半文明国」とみられていたアジア地域の国々にも西欧の諸国と同じ可能性があることを認識させるきっかけとなった、世界史的にもきわめてエポックメーキングなできごとだったということができます。
そして、それを可能にした原動力が、維新以来の富国強兵政策を支えた殖産興業であり、日本の「ものづくりの力」であったと言えます。欧米列強の支配体制という世界のパラダイムを大きく変革する源泉に「ものづくり力」があったのです。




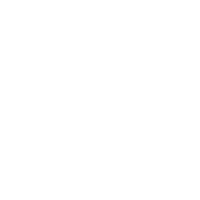 最新情報
最新情報