ものづくり日本の心
第8章:日本のものづくりの潜在力
文:梶 文彦写真:谷口 弘幸(Penthouse STUDIO)
■目次
ものづくりのゆくえ
ここまで、私たちがものづくりや仕事とどのように付き合ってきたのかを、ざっと振り返ってきました。
高度成長、バブル崩壊、失われた20年を経て、いま日本は、アメリカ、中国に次いで、GDPで世界第3位の位置にあります。
人によって、この位置にあることをどう考えるかさまざまな意見がありますが、私は、国土面積が25倍もあり、人口も13億人、3億人と日本の1.2億人と比べると圧倒的に多い両大国と張り合って、小さな日本もなかなか頑張っているではないかと、この国を頼もしく思います。
ご紹介してきたように、日本人は「ものをつくる」ということに対して、強いこだわりを持っている、世界でも数少ない国民です。
第3章で、日本のものづくりの底には、特有の通奏低音が静かに流れていて、この通奏低音こそが、日本の伝統と文化から生まれたものづくりの特徴だと述べました。
日本が持つ緻密で高品質な製品づくりの仕組みは、日本の伝統文化に西洋の科学技術や合理性が融合して生まれた、世界でもきわめてユニークな文化であり、日本でしか実現できない日本の財産です。そしてそれは同時に、世界の、人類の財産でもあります。
今後、世界では、高度な医療な医療機器や宇宙航空分野での機器が求められています。そのために必要なのは、さらに1ケタも、2ケタも精度の高いものづくりを実現する技術の開発です。
日本の将来を考えたとき、ものづくりはいったいどのような役割を果たすのでしょうか。この点に関して、大きく2つの意見があるようです。
ものづくりへのこだわりこそが、日本の産業が先に進むことを阻害している弊害だという意見があります。
- 高度なものづくりこそ日本の産業を支える生命線であり、これからもものづくりにこだわって高度化を進めていくべきだとする意見と、
- いつまでもハードウエアの加工技術にしがみつかず、ソフト・コンテンツなどの情報通信産業や金融・流通・サービス産業の方向に進むべきだとする意見です。
もし、これが日本のものづくりが人類の財産であるとするならば、この財産をさらに高度なレベルへとブラッシュアップしてゆく仕事は、私たちに課せられた責務と言えるでしょう。
ガラパゴス化する? 日本のものづくり
日本の製造業は競争上の優位性はグローバルにみても高いはずですが、市場では優位性を失い、新しい産業も興らず、自動車を除いては市場では負けるという結果になっています。内装部品としては活用されていても、完成品としては、後塵を拝してしまっています。そのため、日本のものづくりは、ガラパゴス化していて、グローバな競争に勝てないという意見が聞かれます。
ガラパゴスといわれる理由として、
①半導体やスマホ、EVなどでグローバルな競争で押されて苦しんでいる、
②日本企業からイノベーションを興すような新製品が生まれてこない
の2つが言われています。
果たして本当に日本ものづくり力はガラパゴス化しているのでしょうか?
日本のものづくりが負けているのではなく、企業のマネジメント力が負けているのであって、課題は高度なものづくりの力を活かして成果に結びつけられない「マネジメント力」にあるといってもいいでしょう。
かつて日本が強さを誇っていた半導体産業や家電産業などの分野で、日本はアメリカや韓国や中国の企業の後塵を拝しています。熾烈な競争を展開しているライバル企業の多くは、日本製の高度な部品やシステムを使い、それが、製品の品質や特性・機能を支えるカギになっていたりします。
日本の最先端のものづくり技術がうまいマネジメント力を得れば、グローバルな競争力をもつことは難しくないでしょう。世界でオンリーワンの高度な技術力をもちながら、日本が市場を奪われている原因は、その技術力や高品質づくりのノウハウを活かしたビジネスモデルを確立できなかった、マネジメント、つまり経営の問題があることがわかります。
ガラパゴス化していると言われている2つ目の「②日本企業からイノベーションを興すような新製品が生まれてこない」というと研究開発力、技術力が足りないと言われそうですが果たしてそうでしょうか。
かつて、日本の産業界は、カメラ、時計、トランジストラジオ、ビデオ、ウォークマン、カセットテープ、家電製品、ファミコン・ゲーム、デジタルカメラ、最近ではハイブリッド車……など、さまざまな製品で世界のイノベーションをリードしてきました。
それが、ここしばらく、アップルをはじめとし他企業に後塵を拝しています。
なぜ、こんな状態になってしまったのでしょうか。
日本の製造業の経営者に、当面の課題は何ですかと聞くと、決まって、「技術開発」が高い優先順位であげられます。そして、イノベーションには最先端の研究開発成果が必要で、それがないために自社からイノベーションにつながるような新製品が生まれないという意見が言われます。いま彼らの関心はDXでしょうか?
「第7章 日本人の創造力と独創力」のノーベル賞の受賞者数でみたように、科学技術力・研究開発力では日本と中国や韓国の差は歴然です。そうした企業に商品開発力、市場占拠率で後塵を拝している状態を見れば、研究開発成果がないから市場でイノベーションをおこせない、という理由が成り立たないことは明らかです。
大きな絵を描かない日本の経営陣
例えば、こんな話があります。
いま、タブレットPCは教育の場などにも導入されるようになって、大きな市場を獲得しています。この分野を切り開いたのはアップル社ですが、実は、タブレットPCが商品として販売される数年前、ある日本の企業の技術部門で、キーボードをなくした液晶のPCが試作されていたそうです。まさにタブレットPCです。
「これは面白い」ということで技術部門から、商品開発の提案がなされたそうですが、トップを交えた商品開発会議では、新製品としてゴーは出されなかったそうです。数年後、アップルからiPadが発売され、ヒット商品として市場で飛ぶように売れていくのを横目で見ながら、技術者たちはやるせない気持ちになったといいます。
提案を受けたマネジメント層は、こうしたものへの需要があるという予測ができなかったのでしょう。リスクを恐れたのでしょうか。もしそうだとすれば、経営者としては失格ですが、そうした経営者を評価する機能が、内部にあるのでしょうか?
イノベーションを興すような新製品が日本の企業から提案されない、ものづくりがガラパゴス化している・・・と言われる実体はむしろ、日本の経営者のこういう姿勢にあるのではないかと思います。
全てがこの調子で、新製品が生まれなくなっているというわけではないと思います。しかし、この話しを聞く限り、問題はものづくりではなく、高度なものづくりの技術を活かせないマネジメント力にもあると思います。
日本の企業経営者で偉大な業績を上げた経営者として、松下幸之助、本田宗一郎、井深大と盛田昭夫、稲盛和夫らの名前が挙げられます。もちろん名を挙げるべき人は他にもいますが、彼らはいずれも、ゼロから事業を立ち上げた経営者です。
成長へのプロセスで、失敗を重ねながら幾度かの危機を乗り越えて大きな成功を収めてきました。本田宗一郎は、「99パーセントの失敗があって、はじめて1パーセントの成功がある」と言っています。高い目標を描き、そこに到達することをめざして果敢にチャレンジし、成果を上げてきたわけです。決して失敗せずに高みに到達したわけではありません。たぐいまれなリーダーシップをもって企業を創業し、大きく育ててきました。
リーダーシップ研究で知られる神戸大学教授の金井壽弘はリーダーシップの要件として、大御所の三隅二不二が提唱したPとMを上げ、不動の2次元と紹介しています(*①『リーダーシップ入門』金井壽弘、日経文庫)。
- p:performance 高い目標を掲げ、具体的な方策を提案・実現する
- M:maintenance 目標に向けて計画を更新し、躓く仲間を勇気づけ支援する
の2つです。
創業者たちは、確かにこうした資質をしっかり発揮して企業を育ててきたようですが、残念ながら、成功した企業を受け継いだ経営者の中には、大きな成果を守ることに精いっぱいで、高い目標を掲げてチャレンジするという精神をうまく発揮できない人たちもいるように思います。サラリーマン社長と呼ばれる経営者の中には、経歴を通して失敗しなかったことを自慢する人たちもいます。
新しい領域へのチャレンジを積極的に行い、高い目標を掲げて行動するビジネスマンの宿命は、失敗するということです。企業内での経営者レースでは、この失敗は致命傷になることがあります。失敗しなかったビジネスマンがビジネスよりも人間関係でTOPに昇り詰めることもあることで、そうした経営者は、意欲・目標・理想という面でチャレンジ精神より慎重な行動・判断を優先しがちです。
イノベーションが生まれない要因に、失敗を恐れるあまり、大きな絵を描こうとしない経営者が増えているという要因もあるのではないかと思います。アラビアンナイトと一寸法師の空想スケールの違いを思い出させるような話でもあります。
「Japan in it」のラベル
製造業の本業はものづくりでも、経営者の仕事はものを作ることではありません。経営者の仕事はマネジメントであり、企業の将来像を描き、そこにできるだけ近づけることです。
高い目標を掲げ、企業を上げてその目標を実現することが仕事であり、その出発点はマーケティングです。日本の企業の経営者と、グローバルに成長する海外企業では、この点についての考え方の違いが大きいのではないか。
こんな話があります。
日本企業では、収益を向上させるために、製品のコストダウンの努力を行い、高品質で低コスト化をめざします。それが成功して企業の収益力が向上し、利益が増えることで、企業体質がリーンになったと、取締役会などでも経営者は高く評価されます。
一方、あるグローバルな企業では、同じように製品のコストダウンを行い収益力を向上させ、利益を大幅に増やします。経営者は称賛されるところですが、逆に、その経営者は左遷されてしまいました。
なぜか? 理由は、コストダウンに成功し、収益を増やしたが、その段階で終わって、その先はなかったのか?と問われたのです。競合と比べて収益体質が優れているならば、市場をコントロールできたはずではないか。競合のシェアを奪い、自社のシェアを伸ばす、それによって競合を市場から追い出せなかったのか、と問われたのです。
日本企業の経営者は、収益体質を改善したことで称賛されましたが、グローバル企業の経営者は、収益体質を向上した結果で、価格戦略で市場をコントロールしてシェアをのばし、競合を市場で弱体化しない限り評価されない、ということでした。
こうしたことを象徴する出来事がかつて市場を席巻したことがありました。
「intel in it」事件です。
パソコンにとってCPUは核になる部品です。CPUの性能によってPCの性能が変わります。しかし、PCメーカーは自社では高性能なCPUを開発できません。そこで、他社より優れたCPUを購入できるかどうかが商品の優秀さを左右する重要なポイントになります。
1980年代から1990年代にかけて、PCメーカーは優位性を獲得するために、高性能のCPUの搭載を目指していました。半導体メーカー各社はCPUの開発に躍起になっていたのですが、ここで、先端を走っていたのがインテル社でした、微細加工の技術をベースに高度なCPUを開発し、PCメーカーはこれを組み込んで高性能なPCとして販売していました。
メーカーはこぞってインテル社製のCPUを組み込むことで高い評価を得ていました。しかし、核となるCPUを開発しているインテル社自身のイメージはあまり高くなかったのです。同社が優秀な人材を採用したいと願っても知名度があまりないために、残念ながら優秀な人材をPCメーカーに奪われてしまうこともしばしばでした。
そこでインテル社が知名度向上を目指して1989年に採用したのが、「intel in It」プログラムです。同社がPCメーカーにCPUを納入するに際して条件として、同社のCPUを組み込んだPCに自社のネームロゴの入ったラベルを貼付して出荷してもらうように提案したのです。これはインテル社にとって知名度・イメージを向上させるメリットがあるだけでなく、PCメーカーもまた、高性能CPUを組み込んだPCであることをアピールできるという付加価値があったのです。
「Intel in it」はその後、1991年になると、「intel inside」と変更されましたが、インテル社のイメージはこれによって飛躍的に高まり、優秀な人材が積極的にインテル社を目指すようになりました。

単に、部品として優秀さが認められ、採用されるだけでなく、取引関係ではいつも劣勢に立たされることが多い”下請け会社”が、親会社に対して堂々と「最終製品の優秀さを部品メーカーが支えています」という自己主張をした素晴らしいマーケティング成果で、これこそ経営者の仕事かもしれません。
日本の電子部品は品質が優秀で、世界中の企業に採用されています。高性能な製品を作るためにはなくてはならない部品となっていますが、どこの製品にも「japan in it」「Japan inside」のラベルは貼られていません。内蔵されている部品のブランドを訴求するようなマーケティングをめざす日本の企業はなかなか生まれないようです。
そう考えると、PCメーカーに「intel inside」を受け入れさせたインテルという会社の存在感のすごさを思わざるを得ませんが、それを実現させられるかどうかは最終的には企業のトップにかかっていることは言うまでもありません。
イノベーションを生む条件
イノベーションについての誤解もあります。
企業が、市場でイノベーションを興すような新製品を開発するためには、どのようなプロセスが必要なのでしょうか?
たとえば、ウォークマンなど、過去にイノベーションを起こした商品をみてみましょう。
これらはいずれも、かならずしも、新しい技術開発とともに商品化された商品というわけではありません。
既存の技術を組み合わせ、その中の、ある機能に特化して商品化し、ユーザーとのインターフェースに独自のデザインを施すことで、消費者に未体験の新鮮な価値や喜びを提供する、つまり、開発者の発想やニーズが起点となって、既存の知識、技術を組み合わせて作られた商品なのです。
新しい研究開発の成果がもとになって生まれたシーズ型の商品ではないのです。
もちろん、素材産業などでは、炭素繊維のように研究開発力がベースになって生まれるものもありますが、消費財マーケットで見れば、むしろ既存の技術を巧みに応用した商品が多いのです。
経済学の巨人シュンペーターは、1926年に著した「*②経済発展の理論」(東畑精一ほか訳、岩波書店)で、経済の成長は、
「新結合」によっておこされ、「新結合が非連続的に表れる限り、発展に特有な現象が成立する。・・・けっして科学的に新しい発見に基づく必要はなく・・・新結合の遂行およびそれを具体化するものの成立は、原則としてけっして利用されていない生産手段を結合しておこなわれると考えてはならない。」(「経済発展の理論」岩波書店)
と書いています。
当時はイノベーションということばはなく、イノベーションに近い大きな変革を非連続の発展とよんでいた。そして、シュンペーターは、非連続の発展は、新しい科学的な発見によってではなく、既存のものを“新しく”組み合わせること(新結合)によって起こされると言っているのです。
よく見ると、ジョブズの商品開発がまさにこのやり方なのです。
必要なのは、ゼロからの技術開発ではなく、既存商品・技術に新しい価値を見つけ、その価値を形にして提供することであり、イノベーションは科学的な新しい発見から始まるという思い込みが、日本からイノベーションを生まれにくくしているのではないかと思います。
スティーブ・ジョブズは、新製品開発の世界で、イノベーションを起こし続けた一人ですが、彼がどのように商品を開発してきた、少し振り返ってみましょう。
ジョブズに見るイノベーション手法
ジョブズは、1976年アップル社を立ち上げてアップイルコンピュータ、APPLEⅡ、Macintoshなどを開発して成功した後、1985年にアップル社を追われます。
そして、傾いた同社を再興するため1996年に再びアップル社に復帰し、POWER PC、iMACを生み、二〇〇一年にはApple Storeを開店し、さらに、〇三年に音楽の分野に進出して、携帯音楽プレーヤーiPod、iTunes、を開発。07年にはスマートフォンのiPhoneを市場に投入、10年にはiPadを送り出し・・・と、デジタル時代における新しいコンテンツの楽しみ方を、矢継ぎ早に提案し、どれも大ヒットとなりました。
こうした流れをみると、ジョブズがオリジナリティあふれる新しい商品を提案してきたように思えますが、ジョブズ自身は決してそう思っていなかったようです。
早稲田大学商学学術院教授の井上達彦によると、「米オハイオ州立大学教授のオーデッド・シェンカーは、著書『Copycats』において、アップルを「アセンブリー・イミテーションの達人」と評し、
「よそで開発された技術を結びつけて、優美なソフトウエアとスタイリッシュなデザインで包み込む。他社の技術やアイデアを持ち込むことを恐れず、ちょっとひねりを加えて自社の魅力的な製品を作り出す。そういった強さを持っているのがアップルです。」(『*③アップルの本質は模倣の達人』「日経ビジネス」(2012年3月21日))。
と紹介しています。
既存の技術を新しいコンビネーションで結びつけ、アッセンブリーで商品化するのが上手な企業だという意味です。
実際に、ジョブズは、模倣することについて肯定的で、
「素晴らしいアイデアを盗むことに我々は恥を感じてこなかった」
「優れた芸術家は真似し、偉大な芸術家は盗む」
などのことばを残しています。
ただ、単に模倣するだけでなく、彼の商品には、新しい価値を発見し、独自のデザインを加えているなど、ジョブズならではのこだわりが込められているのです。
マイクロソフトも、いくつかアップルのシステムを模倣していますが、ジョブズは、
「マイクロソフト社がマックをコピーすることに長けていたわけではない。マックが10年もの間コピーしやすい製品だっただけだ。それはアップル社の問題だ」(前掲書③)
と語っています。
『Copycats』の著者であるシェンカーも、「イノベーションとは必ずしも何か新しいものや技術を発明すること自体を指すわけでなく、既にある技術やアイデアを組み合わせて、全く新しい技術や製品・サービスに昇華する力を指すのだと考えています。イノベーションとは、組み合わせる力であり、「連結力」であるということです」と書いています。
とはいえ、そうして生み出したものが、単に形状や技術の模倣に終わらず、消費者の生活様式を変えてしまうほど、まったく新しい価値を提供する商品に仕上がっているところが、ジョブズのイノベーションの深さといえるでしょう。模倣から出発して、最後には、それまでになかったまったく新しい価値を生み出しているのです。
チャンスは「ニア・ハイ」にあり
しばらく前ですが、この原稿を書いているときに、偶然こんな話を読みました。いろいろなことが想像されて、ちょっと面白かったのでお付き合いください。
最近はだいぶ改善されてきましたが、かつてサッカーの国際マッチでは日本チームの決定力のなさがよく指摘されました。ヨーロッパの強豪チームなら確実に一点獲得というところで、日本チームはしばしばゴールを外し、惜しい試合展開になるというのが、デジャヴのようなお決まりのパターンでした。
それに比べて、メッシやロナウドなど、世界的なストライカーのゴール決定力は圧倒的だというのは評論家・中村僚でした(*④「フットボールチャンネル」2013年6月8日)。
日本のストライカーと彼らとの違いはどこにあるのか。中村によれば、一般にサッカーのゴールには、いくつかの種類があるそうです。
ゴールとなるシュートにはいくつかパターンがあること。私はこれを大きく3つに分けることができると判断した。
[一]GKの予測を上回り、物理的にセーブ不可能なコースへのシュート:ゴールキーパーがとどかないゴールマウスぎりぎりのミドルシュートや、鋭利なカーブを描いた直接フリーキックなど。
[二]GKの予測すら不可能にするシュート:ゴールキーパーが反応できない、視覚外から放たれたシュートやフェイントでゴールキーパーを抜き去ってから放つシュートなど。
[三]予測も物理的対処も可能だが、反射的にセーブすることが困難なコースへのシュート:別段、球速があるわけでもなく、タイミングをずらした形跡もない。それでもあっさりとゴールに収まるシュート。具体的には、ゴールキーパーの顔の横や肩口、股間、倒れ込んだ際の脇の下など、一部で「ニア・ハイ」と呼ばれるシュート。(「フットボールチャンネル」2013年6月8日)
そして日本のJ1、J2でのゴールと、メッシ、ロナウドのゴールを比較したところ、
[一]のゴールは、メッシが六八%、ロナウド七〇%、Jリーグが七〇%と変わらない、
[二]では、メッシ、ロナウドは共に一二%、Jリーグが二二%と差があり、
[三]はメッシ二〇%、ロナウド一九%に対して、Jリーグは八%止まり
つまり、日本の選手はGKから遠いコーナーや死角を狙って外してしまうケースが多いが、メッシらはゴールキーパー近くの「ニア・ハイ」を狙い成功させる確率が高いという。
そして、このことを少年サッカーチームに教えて、ニア・ハイを狙わせたら、得点力がグーンと上がった、というのです。
サッカーのゲームに関して、紹介されたような内容が本当に正しいのか、私に判断する力はありません。しかし、この話、なにやら、ゼロから研究開発に取り組んでヒット商品を出そうとしてもなかなか出せない日本の企業と、既存の技術(ニア・ハイ)を組み合わせて、ヒットを連発するジョブズとの違いを、ほうふつとさせるような話ではありませんか。
そういえば、ウォークマンはテープレコーダーのニア・ハイにあるものですし、iPhoneも、iPadも、当たり前に存在した商品からかけはなれたまったく新しい商品というわけではありません。
独自の価値を生む、換骨奪胎と合わせ技
異なったものを合わせ、つなぎ、結びつけ、それまでになかった新しいものに姿を変えるという行為は、日本人が伝統的に親しんできたものです。
わたしたちは、古くから、貝合わせ、歌合わせなどの遊びをしてきました。また、炊き合わせ、抱き合わせなど「合わせる」行為も多く行ってきました。
岩波書店の「逆引き広辞苑」(*⑤岩波書店、第一版)を見てみると、「○○あわせ」ということばは「歌合せ」をはじめ一三〇もあり、「合わせ××」も合わせ鏡など二〇近く。同様に、「○○結び」も花結び、蝶結びなど一〇〇近く、「○○つなぎ」は顔つなぎ、数珠つなぎなど一八が掲載されています。この語彙の豊かさと自在さは、驚異というしかありません。これは私たちの発想の多様さと自在さを示すものです。
異なったものを組み合わせ、結びつけるという行為をこれだけ多様に行ってきたのは、逆に言えば、私たちが遠い昔から、組み合わせ、結びつけることから生まれる新しい発見、驚きに価値を見つけていたということです。こうしたことを楽しめる感性、知性、創造力を備えているということにほかなりません。
生産技術力の基本は、素材、工具、加工法、技能をいったんばらして、組み合わせ、結びつけ、つなぎ、そのうえでインターフェースを工夫することで成り立っています。
知日家で、構造主義の旗手と言われたフランスの哲学者ロラン・バルトは、その著書『表象の帝国』(*6宗左近訳 ちくま学芸文庫)で、
「《天ぷら》はポルトガルの、もと、四節句中の肉断ち(テンポーラ)の料理に由来する」と紹介した後で、「だが、日本人の例の換骨奪胎の技術によって洗練されて、これはもはやそれとは別な場合の食べものとなっている。」(『表象の帝国』ちくま学芸文庫)
と書いています。
換骨奪胎とは、元にあるものをいったんバラし、他の要素と結びつけ、つなぎ合わせて再構成することです。その結果、模倣の枠を大きく超えて新しい価値を持った、別のものが生みだされます。
そこに新鮮な楽しみや刺激があり、ユーザーに合わせて洗練されたインターフェースをデザインすれば、それはジョブズが行ってきた行為そのものではありませんか。
テンポーラの知識なしに、ゼロから天ぷらを考案するのは、至難の業です。そして、だれでもが、テンポーラから天ぷらを作りだせるわけではありません。模倣を越えてイノベーションへと昇華させるには、その過程で、「新しい価値」への気付きと、求めるゴールを創造するデザイン力が不可欠です。
前述のように、ジョブズも「素晴らしいアイデアを盗むことに我々は恥を感じてこなかった」、「優れた芸術家は真似し、偉大な芸術家は盗む」と語っています。。
開発に際しては、ユーザーの新鮮な驚きや喜びを優先し、仕上がりの微妙な質にこだわり、何度でも修正を要求してスタッフとぶつかったそうです。こうした仕上がりへのこだわりは、若いころから傾倒した禅や、深い関心を持った日本の工芸品に大きく影響されたと言われています。
ジョブズのイノベーションを生む斬新な発想は、もしかしたら、西欧流の合理性と日本の伝統的な美意識という、異なった価値観が融合することで生み出されたものなのでしょうか。。
フランスの印象派も、浮世絵に刺激されて、新たな境地を開き、絵画史の歴史に残る作品を数多く残しました。これもシュンペーターいうところの新結合の成果ということになるのかもしれません。
異質な文化や価値観を共有する
改めて、私たちの過去から続く、ものづくりへのこだわりを見ていると、日本人は、もしかすると、ものづくりを高度化するために生まれてきた民族ではないかと思うほど、ものづくりのプロセスに抱く関心の強さは超弩級です。
わたしたちがこれまでに作り上げてきた高度なものづくりの技を、未来に向けてさらにブラッシュアップしていくことが重要だということについて、どなたも異論はないと思います。
国内からものづくりの場が消えつつあるなかで、日本のものづくりは終わりだという人がいますが、わたしは、まだまだ大きな可能性を秘めていると考えています。というよりも、むしろこれからが日本の感性を世界にアピールする本番ではないかと思います。
これまでわたしたちは西洋の科学技術を礼賛し、どちらかと言えば伝統的な考え方や行動様式を古いもの、劣るものとして退けてきました。
しかし、私たちが古いものとして退けてきた日本古来の伝統の上にあるものは西洋の文明から見ると、これまで全くなかった、新しいもの、新しい文化や価値観を持った新鮮なものであるという認識が欧米から表明されるようになってきました。文化遺産に登録された和食の世界、素材を加工し、味わうそのやり方もその一例です。
一神教に対して、万物に神が宿るとする発想は、西洋思想から見ると、目からうろこのものでしょう。地球にはさまざまな民族が住んでいます。一つの価値基準ですべてを序列化するのではなく、それぞれの民族が独自の価値基準と文化を持って共存する、いわば、八百万の神の存在が、地球の共生という観点からも自然な発想であることは言うまでもありません。
それはある意味で、これまで競い合うことで自己の正しさを主張し合ってきた西洋の文明が、自分たちと価値観を共有しない他者の存在とそのもつ異質な価値観を先入観なく認め始めたということかもしれません。多様な森がエコロジカルに安定するというのは自然の摂理です。
西欧の文明が、明治以来、異質の存在として列強の仲間入りしようとしてきた東洋の小国に対して、その文化や価値観を理解するまでに一五〇年という時代が必要だったということでしょうか。コミュニケーションを正しくかわすということが、いかに長い時間を必要とするものかということかもしれません。
グローバルなイノベーションを起こすために
これまで私たちは、多くの文化や技術を欧米始め、多くの国から学んできました。そして、欧米も、アジアのもつ異質さ、その価値観に目を向けようとしています。
いまやIT技術の高度化によって、空間的な距離をものともせず、コミュニケーションすることを可能にしてきました。また輸送機器の発達によって、物理的な移動も、つい60年ほど前までは東京から大阪へ出張するのに8時間もかかり、一泊が必要だったことさえ信じられないほど手軽になりました。
距離という障害が亡くなり、また、国境という障害が開かれるようになったいま、市場は国内より、国外を包含して広大になっています。そんな時代には企業の思考・行動範囲もよりクローバルなものが求められます。
1978年、鄧小平が中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議で打ち上げた改革・開放政策を受けて、安価な労働力を求めて、多くの国の企業が中国に進出し、ものづくりの場が国内から海外に移動しました。中国の開放政策に刺激されて、多くのアジアの国々でも改革が進められ、ものづくりの現場は滝つぼに水が流れ落ちるように、アジアへと移っていきました。
そうした国々では、産業の発達とともに、給与所得者が育ち、いまや、製造の場としてだけではなく、購買力を持った消費市場として重要な意味を持つようになりました。大きなマーケットをもつそうした国々と良好なビジネスを展開するためには、お互いの理解が不可欠です。
アメリカも、ヨーロッパの国々も、もともと海外からの移住者が多く、あらゆる世界で、いわば異文化を持った人たちが、活躍しています。アメリカの企業を訪ねれば、事務所にいる人材の半分は、ヨーロッパ出身だったり、南米、アフリカ出身だったり、あるいはアジア出身だったりします。そうした人材がせめぎ合っているのがアメリカ社会です。
またヨーロッパも同様です。ヨーロパは元々地続きで、人材の交流は活発でした。西欧の国々にも東欧の人材は溢れ、植民地を持っていた過去からアフリカ、南米、中東、アジアの人材もかなりの比率で住んでいます。さらに、いまはEUが域内の人材に国境を開放していますから、EU加盟国の企業の事務所は異文化人材の宝庫と言ってもいいでしょう。海外の企業では、多くのグローバルな人材がグローバルな市場をめざして戦略を検討し、活動を展開しています。
ひるがえって、日本を見ると、日本の企業では事務所にいる人材は、最近は変化したとはいえほぼ100パーセント日本人です。企業は海外進出をめざしてグローバル戦略を立案し、盛んにグローバルを対象にした商品を開発し、マーケティング活動を展開しています。
グローバルな市場をめざして・・・と言いながら、日本の企業で戦略を検討するのは日本人ばかりです。果たして、こんな状況で本当に日本の企業は海外の企業とグローバルな市場で競争できるのでしょうか?
いま、日本ではさかんにグローバル人材の育成が叫ばれています。日本の国も、海外に門戸を開き、人材の交流を進めるために、留学生の誘致を進めています。文科省が進める目標は、2020年に30万人の留学生を招へいすることですが、さまざまな施策によって、2013年に18万人だった留学生数は、2016年には、20万人を突破しています。
日本で学ぶ留学生数は順調に増えているのですが、残念なことに、そうした留学生の多くが日本で働くことを希望しながら、30パーセントほどの人材が、就職先が見つからずに他国で就職したり帰国してしまったりしていることです。
せっかく優秀な人材が日本の企業で仕事をすることを望みながら、受け入れる企業がないのです。理由は、日本語を十分に理解できないから、あるいは、外国人を雇用しても、彼らの能力を発揮してもらうことができないから。わかりやすく言えば、文化と価値観の違う人材は社内のトラブルのもとで、逆にこれまでのやり方が侵され、問題が生じるため、敬遠する・・・というわけです。
イノベーションとは異質な価値観がせめぎ合う所から生まれるのだと思いますが、異質な価値観のぶつかりを、マイナスとして避ける文化が日本の企業にはあるのですね。これを克服しないと、これからのグローバルなイノベーションはなかなか起こせないのではないかと思います。
多くの価値観のせめぎあいと、高度な頭脳がまじりあう所から、新しいイノベーションは生まれます。優秀な頭脳と異なる文化・価値観を持った留学生を、今後、いかに日本の企業に取り込めるか、ITの進歩で、ますますグローバル化が進むなかで、新しい時代にリーダーシップを発揮するために、不可欠な要素ではないかと思います。
日本のものづくりの底力と潜在力
万物に神が宿る、最近ではトイレにさえ、それはそれはきれいな女神さまがいるとする日本人の発想は、共生という切り口で見れば、宗教的というよりも魂のコスモロジーという方がふさわしいひろがりをもっています。
八百万の神や、ロラン・バルトが言う換骨奪胎、さらには融通無碍、清濁併せのむ、お客様は神様です、などという言葉は、例えばフレキシビリティやダイバシティ、カスタマー・サティスファクションといま風のことばで言い換えてみると、それはグローバルな時代にも通じる最先端の考え方になります。そしてこれらは、日本人には、長い歴史のなかで使い慣れてきた土着の思想でもあります。
たとえば、こんな商品をご存知でしょうか。
お湯をさすだけで食べられる、生みそを使ったインスタントみそ汁があります。あるメーカーの製品の10食パックは、生みそと具の小袋が10個ずつ入ったものですが、みそと具の小袋が、みそ10個/具10個とまとめて10個ずつ入れられているのではなく、みそ具みそ具・・・と1個ずつ交互に並べられています。
購入した客は、調理に際してみそと具の袋を1つずつ取り出す必要はありません。隣り合った任意の2袋を取り出せばみそと具が1つずつ取り出せるようになっているのです。異なったものを交互に隣り合って封入するためには、生産工程でひと手間多く必要ですが、そんなサービスに価値を認めてコストをかけるのは、日本くらいでしょう。
そうしたサービスにどれほどの価値があるのか、と問うのが、これまでの西洋の合理思想です。しかし、そんな彼らが、いまは、日本式のゆるい、実は高度に仕込まれたおもてなし発想に価値を見出し始めています。洗浄トイレの人気なども、言うまでもなく、日本のおもてなし精神から生まれた商品と言えるでしょう。
西欧の人たちも、すごいですね。文明の最先端を走りながら、あらゆるきっかけを利用して、新しい価値を求め、受け入れて、自らを変えようとしています。
いま、「おもてなし」や「もったいない」などのことばが海外でも話題になっています。最近は、日本の価値観から生まれた新しいサービスや行動様式を心地よいと感じる外国人も増え、日本に駐在したビジネスマンたちのなかには、帰国する際のみやげに洗浄トイレを買って帰る人も少なくないそうです。中国人の爆買いもその一例でしょう。かわいさテンコもりで楽しさを演出する、しかもおいしい日本製のお菓子は海外でも大人気のようです。
西欧の科学技術や合理性を導入し、精いっぱい活用してきた私たちが、ものづくりやマネジメントをはじめとする世界で、改めて日本古来の伝統的な共生の発想や行動様式を活かして新しい価値を提案していくのは、これからです。やっと、その緒についた所です。
まだ、私たちには、私たち自身が気付いていない大きな潜在力、可能性があります。やっとそうしたものが力になる時代がきたと言っていいと思います。ニア・ハイに果敢にチャレンジする柔軟な思考とマネジメント力、新事業開発力を見直すことで、日本のものづくりが本当に力を発揮するのはこれからなのです。




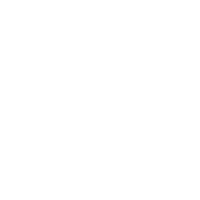 最新情報
最新情報